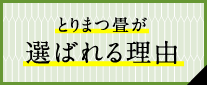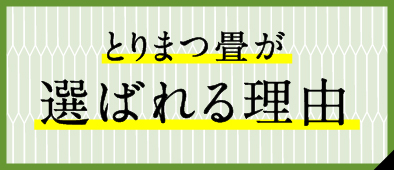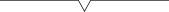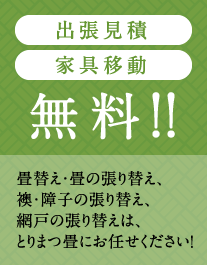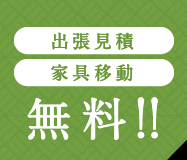「洋室を和室のように利用したい」「フローリングの一部に畳スペースを作りたい」という方は、置き畳を使ってみてはいかがでしょうか。
置き畳(ユニット畳)とは、床に直接敷いて使える、薄型の畳のことです。本記事では置き畳のメリット・デメリット、購入する前に押さえておきたいポイントを紹介します。
畳のある暮らしを実現したい方、置き畳を購入すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
置き畳(ユニット畳)のメリット
置き畳には、以下のようなメリットがあります。
自分で簡単に設置できる
置き畳は一般的な畳よりも軽いため、新しい置き畳の設置、レイアウトの変更も簡単です。使わなくなった置き畳は、別の部屋に敷き直したり、収納スペースに片づけたりすることもできます。
サイズやデザインの選択肢が多い
お部屋の広さや使用目的に合わせて、置き畳のサイズや枚数を調整できます。カラフルで明るい印象のもの、落ち着いた色味のものなど、多彩なラインナップのなかから選択可能です。
クッション性がある
フローリングの床と比べると、置き畳のほうがクッション性に優れています。お子さんやご高齢の方がいるご家庭でも、ケガをしにくいのがメリットです。踏み心地がやわらかいため、足の疲れも軽くなるでしょう。
防音効果が期待できる
マンションやアパートにお住まいの場合は、お子さんが走り回る足音、物が落下する音などが気になるものです。そこで、クッション性のある置き畳を敷くことで、下の階への騒音を軽減できます。
置き畳(ユニット畳)のデメリット
続いては、置き畳(ユニット畳)のデメリットを見ていきましょう。
置き畳の継ぎ目にゴミが入る
置き畳を掃除する際は、継ぎ目の奥に入り込んだゴミまで取り除かなくてはなりません。置き畳をはがして、継ぎ目や畳の下に詰まったゴミを定期的に除去する必要があるでしょう。
歩いたときに畳がズレる
フローリングと置き畳の相性が悪いと、歩いたときに置き畳がズレてしまいます。敷き直しの手間が発生するだけでなく、摩擦によってフローリングが傷付くこともあるため、注意が必要です。
カビが繁殖するおそれがある
イ草の置き畳を湿気の多い環境に置くと、カビが発生するおそれがあります。置き畳の下にカビが生えてしまい、気付かないまま放置するケースもあるため気を付けましょう。湿度が気になるようなら、防カビ機能のある置き畳、カビに強い樹脂製、和紙製の置き畳がおすすめです。
置き畳を購入する際のポイント

置き畳を新たに購入する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
床材の種類をチェックする
まずは、設置する部屋の床材を確認します。フローリングには、丸太から切り出した木を貼り合わせることなく、1枚の板に加工した、「無垢フローリング」と、複数の素材を貼り合わせて加工した「複合フローリング」があります。
幅広く利用されるのは安価な複合フローリングですが、滑り止めが効きにくい場合があるため注意が必要です。ズレが気になるなら、滑り止めの付いた置き畳を選択する、置き畳用のジョイントを使うなどの対策を行ないましょう。
一方の無垢フローリングは、天然木100%で素材がやわらかい傾向にあるため、置き畳との摩擦で傷が入るおそれがあります。
置き畳の素材を選択する
置き畳の素材として代表的なのは、イ草、和紙、樹脂(ポリプロピレン)の3種類です。
イ草製の置き畳には、畳ならではの湿度を調整する機能や、リラックス効果が期待できます。本物の和室のような香りや、畳の質感を楽しみたい方は、イ草製の置き畳を選ぶとよいでしょう。
お手入れのしやすさ、耐久性を重視する方には、和紙製か樹脂製の置き畳をおすすめします。傷や汚れ、変色、水濡れに強いだけでなく、カラーバリエーションが豊富な点も魅力です。
関連記事:
畳のメリット・デメリット│イ草畳、樹脂畳、和紙畳の違いを徹底解説
適切なサイズを選択する
敷きたいスペースに合わせて、置き畳のサイズと枚数を検討します。部屋の一角に畳を敷くのか、部屋全体に置き畳を敷き詰めるのかで、必要な枚数は変わってきます。イメージ通りに置き畳を設置できるよう、室内の採寸は慎重に行ないましょう。
模様替えを頻繁に行ないたい方には、小さめサイズの置き畳が、掃除の手間を極力かけたくない方には、サイズの大きい置き畳がおすすめです。
まとめ
置き畳には、軽量で運びやすい、レイアウトを自由に組める、クッション性や防音性に優れているなど、数多くのメリットがあります。置き畳をうまく取り入れて、和の情緒を感じられる快適な空間を作りましょう。
畳の張り替えや新調をご検討されている方は、ぜひお気軽にとりまつ畳にご相談ください。
TEL:0120-211-021